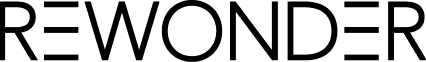クリニックの外観は患者様の第一印象を大きく左右し、集患や信頼感にも直結します。なぜなら、初めて訪れる方にとって外観はクリニックの“顔”であり、清潔感や親しみやすさが伝わることで来院のハードルが下がるからです。
本記事では、クリニックの外観デザインの基本的な考え方から、実際に設計で求められる要素まで詳しく解説します。理想のクリニックづくりを目指す方は、ぜひ最後までご覧ください。
クリニック外観デザインの基本的な考え方
はじめに、クリニックの外観デザインで重視すべき3つの基本的な考え方について詳しく解説します。
内装との統一感をもたせる
クリニックの外観と内装には、統一感をもたせることが重要です。
患者様は外観を見てクリニックの雰囲気や診療内容を想像しながら来院しますが、実際に中へ入った際にギャップを感じると、無意識のうちに不安や違和感を覚えることがあります。例えば、外観がモダンで洗練されているのに、内装が古めかしく雑然としていれば、期待感が裏切られた印象を与えてしまいかねません。
ロゴやサイン、壁材や照明など細部にまで配慮し、外観と内装を一貫した世界観で設計することが、患者の信頼獲得とリピートにつながります。
診療内容や来院する患者層に合わせる
クリニックの外観デザインは、診療科目やターゲットとなる患者層に合わせて最適化することが大切です。
例えば、小児科であれば明るくカラフルな色使いや親しみやすいイラストを取り入れることで、子どもや保護者が安心して来院しやすくなります。一方、内科や整形外科など高齢者の来院が多い場合は、明るい色調や見やすいサインなどを重視する必要があります。
また、美容クリニックや心療内科など、プライバシーを求める患者層には人目につきにくい立地・入口の工夫が求められるでしょう。
診療内容ごとの患者の特性やニーズを的確に捉え、それを外観デザインに反映させることで、ターゲット層から選ばれるクリニックを実現できます。
競合医院との差別化を意識する
近隣に同じ診療科のクリニックが複数ある場合、外観デザインによる差別化は集患に直結します。差別化のためには、単に派手なデザインにするのではなく、クリニックの理念や強み、提供したい価値を明確に打ち出すことが重要です。
例えば小児科なら、外観に明るい色使いや親しみやすいキャラクターを取り入れることで、他の小児科にはない「親しみやすい場所」として記憶に残り、選ばれる理由となります。
ただし、看板やサインの色使いについては、地域の景観条例により使用できない色がある場合もあるため、事前に確認が必要です。外壁の素材、植栽や照明など、規制の範囲内で細部にまでこだわることで、他院とは異なる独自性を演出できるでしょう。
参考事例:おぎくぼ小児科
クリニックの外観デザインに求められる要素
クリニックの外観デザインを考える際には、単なる見た目の美しさだけでなく、患者様が安心して来院できる環境づくりや、地域との調和も大切なポイントとなります。ここでは、クリニックの外観デザインに求められる要素について詳しくみていきましょう。
わかりやすさ・視認性の高さ
クリニックの外観でまず重視すべきは、「ここが医療施設である」と一目でわかる明確さと視認性です。
患者様は体調が優れない状態で来院することが多いため、迷わずにたどり着けることが大きな安心につながります。看板やサインは遠くからでも認識しやすい大きさや配置にし、クリニック名や診療科目、診療時間などの基本情報をしっかりと表示しましょう。ロゴやブランドカラーを効果的に使うことで、地域の方々に認知されやすくなります。
ただし、地域によっては景観条例により看板の色や大きさに制限がある場合があるため、設計時にはプロに相談することをおすすめします。
安心感を与えるデザイン
医療施設として、患者様に安心感を与える外観デザインは極めて重要です。白やベージュなどの清潔感のある色を基調としつつ、温かみのあるアクセントカラーを加えることで、親しみやすい印象を作れます。
素材選びでは、自然素材である木材や石材を部分的に使用することで、無機質になりがちな医療施設に温かみを加えられます。また、季節の花や緑豊かな植栽は、訪れる人の心を和ませる効果があります。
エントランスには十分な大きさの庇(ひさし)を設け、雨の日でも落ち着いて入館できる配慮も大切です。
バリアフリー設計
すべての患者様が安全かつ快適に利用できるよう、バリアフリー設計は欠かせません。スロープを設けない(段差のない)設計を目指すことが基本ですが、やむを得ずスロープを設ける場合は各自治体の福祉のまちづくり条例で定められた基準を確認し、基準を満たした設計を行いましょう。
そのほかエントランスドアの有効開口幅や身障者用駐車スペースの幅についてもバリアフリー法や各自治体の条例により具体的な数値基準が設けられているため、設計時には必ず最新の基準を確認し、適切に対応することが重要です。
参考:東京都福祉のまちづくり条例について(全体の流れなど)|東京都福祉のまちづくり条例|東京都福祉局
受付までの導線
外観から受付までの導線は、初めて来院される方にもわかりやすく、ストレスなく移動できるよう設計しましょう。
例えば駐車場からエントランスまでの動線はできるだけ短く直線的に計画し、分かりやすいサインで視覚的に誘導します。雨天時の対策として、主要な動線には可能な限り屋根を設置しましょう。タクシーや送迎車での来院に配慮した車寄せスペースの設置も効果的です。
立地や周辺施設との調和
クリニックは地域社会の一員として、周辺環境や景観と調和したデザインが求められます。住宅地では過度に派手な色彩や大きすぎる看板は避け、周囲の建物や自然に馴染む色や素材を選ぶことが大切です。敷地の緑化や植栽を取り入れることで、患者様だけでなく地域住民にも親しまれる雰囲気を演出できます。
また、騒音や照明、駐車場の配置などにも配慮し、近隣住民への影響を最小限に抑える設計を心がけましょう。こうした地域との調和は、長期的な信頼関係の構築にもつながります。
なお、地域によっては景観条例により使用できる色や看板の大きさに制限がある場合があります。外観デザインを検討する際は、クリニック開業に必要な設計・施工をワンストップで対応するREWONDERにご相談ください。
まとめ
クリニックの外観は、医療施設としての理念や信頼感を伝える場でもあります。今回紹介したポイントを参考に、地域に愛され信頼されるクリニックをつくりましょう。
医院開業を検討されている方は、内装業界28年・医療施設内装のプロであるREWONDERにご相談ください。REWONDERは、医療施設内装の豊富な実績と専門知識を活かし、診療科目ごとに最適なオペレーションや収益化を意識した設計・デザインをご提案します。
物件調査や交渉、設計・施工、家具や備品の選定、ロゴデザイン、さらには開業後のアフターフォローまで、ワンストップでのサポートが可能です。
医療施設内装の豊富な実績から知見専門分野ならではのさまざまなご提案が可能
仲介会社を挟まず、ドクターと100%直接お取り引き
全国どこでも設計・施工が可能